
|
超ウルトラ級答案用紙 土屋 遊 この作品は『低能文学マガジン0点』を創刊する際に書いたモノです。 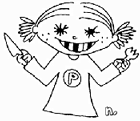 中学の時、私より頭のいい生徒は沢山いすぎたが、その頂点を争っていたのは山川君と賢太郎だった。
中学の時、私より頭のいい生徒は沢山いすぎたが、その頂点を争っていたのは山川君と賢太郎だった。中学生といえば殆どが地域内の生徒で、半数は小学校も同じであるから「あだな」もしくは名字か名前を呼び捨てにされる。だが、山川君はそれほどの風格があったとも思えないのだがあくまでも山川君であった。頭がいいから。 そして何故か、納得の運動音痴であった。頭がいいから。 山川君ちの隣に住むカトキチの情報によると、彼の家では毎日のように親子討論会を開いてるらしい。頭がいいから。 その声は近所中に響き渡る大きな声だと言うことだった。頭がいいから。 しかし、そのわめき散らす大声にもかかわらず、カトキチにとっては内容はチンプンカンプンなんだそうだ。頭が悪いから。 「ふーん、頭がいいやつは声も大きいんだな……」 私たちは意味不明なままゴーインな納得をしたのであった。小学校時代の話である。 ある時、そのカトキチの家に遊びに行くと 「ねえねえ、見てみて」 と何やら怪しげな笑みを浮かべながら彼女は言った。指さす先は、山川君ちの庭にある大きな鳥小屋。きれいな色をしたインコや文鳥に混ざって、雀が一匹ぴょんぴょんと跳びはねていた。 「なにあれ!スズメ?」 私がそう聞くと、カトキチはまるで自分のことのように鼻の穴をふくらましながらこう言った。 「そう。スズメの生態を研究してるんだって」 今考えれば、鳥小屋にいれてスズメの生態を研究するなんて無意味なようにも思えるが、あのすばしっこい鳥を捕まえたということと、「研究」と言う響きは、私たち凡がきに 「はあーなるほど、頭がいいからねー」 と思わせるに十分だった。 そしてまた馬鹿がきどもはマヌケずらをこいて、いつものように妙なこれでもかと感心をしたのであった。 一方の成績優秀くん、賢太郎といえば合唱コンクールを思いだす。 私と彼は中学2年3年と同じクラスであったが、1年の合唱コンクールで歌う彼の姿が私の脳裏に鮮明に残っている。 私は自分のクラスが何を歌ったのかも覚えていないと言うのに、彼らのクラスが歌っていた歌詞まではっきりと覚えているのだ。 彼は一語一語はっきりと、見てるこっちが恥ずかしくなるほどバカ口を開けて、驚くほど大きな声で歌を歌っていた。 「遠いとおいー遥かな道はーつーらいーだろうがー頑張ろうーくーるーしーいー坂もー止まればくだーるー遠いとおいー遥かな道はー銀色の遥かなみーちー」  そして私達は、3年生になった。 そして私達は、3年生になった。入試を控え、クソ真面目連合は席の最前線を占領していた。 おちこぼれ軍団が後ろで大騒ぎしていると、連合軍は気味の悪いほどゆっくりと後ろを振り返り、眼鏡の奥から眼孔の中で魚の腐ったような瞳をぎらりとさせるというささやかな抵抗にでる。 しかし奴等の行動はあまりにもセコイヤチョコレートだ。振り向き攻撃を軍団に気付かれるやいなや、大慌てで前をむきかえる。消しゴムを投げられようが少年ジャンプを当てられようがもう2度と後ろを振り向かない。 彼らの生体の研究してる方が、スズメのそれより遥かに面白かった。 しかし賢太郎は違った。 確かに連合軍の一味でもあるが、授業中でもおかしいときは大声で笑い、放課後もおちこぼれ軍団と一緒になってプロレスやバスケで汗を流していた。 放送室を占拠して好き勝手な音楽を大音量で流すという快挙は、彼の緻密な計画書があってこそ成功した。私が発案した制服ミニスカ運動・ローラースケート登校にも積極的に協力してくれた。 2学期にもなると体育の授業を見学して公式の暗記したり、学校を休んでまで試験勉強するクソが多い中、彼は毎日、元気はつらつに登校していたものだ。 ある時、賢太郎が先生に呼び出された。それが決して良い内容ではないことを先生の口調と冷ややかな目付きが物語っている。 「どうしたのーめずらしいじゃん」 そう聞くと、彼はにやにや笑って中間テストの答案用紙を私に見せてくれた。 答案用紙は全て0点だった。 沢山の赤いバツ印。その周りにはインクがあちこちに飛び散って、採点した者のやけくそぶりが十分に伝わってくる。 先生に何か無言の抗議でもしたのかと聞いた私に、賢太郎はいつものようにゆっくりとした口調でこう答えた。 「違うよお、何事も経験だと思ってね、0点を取ったときの気持ちがどんなものかと思ったんだ」 私は初めて、賢太郎と自分との違いというものに気付いた。 こんな行動は私達にはとれない。いや、故意にじゃなくったって、私達には0点は取れるからだ。取りたくなくてもそうなっちゃうからだ。 「私も頭良くなりたいなーそしてわざと0点を取ってみたい」 まあそう思うこと自体アホまるだしだけどさ。 しかし私はそう言いながら、 (かっこいいなあ) と思っていた。そんじょそこらの秀才ではない。 クソ連合にこのまねができるか!出来るもんならやって見ろ!そして私達おちこぼれ軍団の偏差値向上に関与してみろ! 山川君に妙な感心をしたことは沢山あったが、尊敬したことなど一度もなかった。しかしこの時だけは賢太郎をちょっと尊敬した。そしてすぐに忘れた。 良く考えてみれば、私が頭脳明晰になり故意に0点を取ることなど不可能と同じように、賢太郎がわざと0点を取ってみても、本当に0点を取った時のバカの気持ちは理解できないだろう。しかし、そのチャレンジ精神はチョモランマより高く評価してやる。したい。させてください。 賢太郎はリーダーシップをとってクラスをまとめ、あらゆる行事に積極的に参加し、たまにでる突飛な行動も、私達は妙な感心などしなかった。 それは私達がなんの先入観もなく彼を対等に見ていたからだ。同時に、彼が私たちを対等に見ていたからだとも言える。暗記の数も、脳味噌の構造も、進路も違うけど、同じもので笑い、同じもので怒り、同じ気持ちになれる同じ人種だからだ。 そして私達は、遠い遥かな大してつらくもない灰色の道を歩いて大人と呼ばれる程成長した。 その後の山川君の道のりが何色であったかは知らんが、東大に主席で入学し、ボケ老人のように夜な夜な小さな街を徘徊していると聞いた。 夢遊病者である。 私達は驚いたか。驚かない。私達はそれを聞いてもびくともしない。 「はあーなるほどやっぱりねえ」 と、あいかわらず妙な感心をするのであった。 賢太郎はあいかわらずだ。全くあの時のままだ。 彼が今でも生きていたら、私がこの駄作だらけの「0点」を見せた時、あのゆっくりとした口調で 「やあ、面白いねえ、俺も参加させてくれよ」 と呑気に言うだろう。 私達は、同じ人種だからね。 |